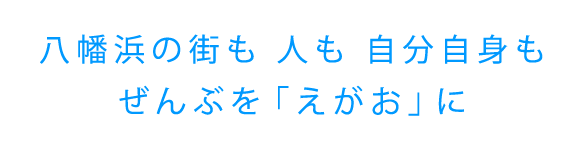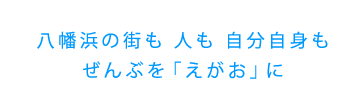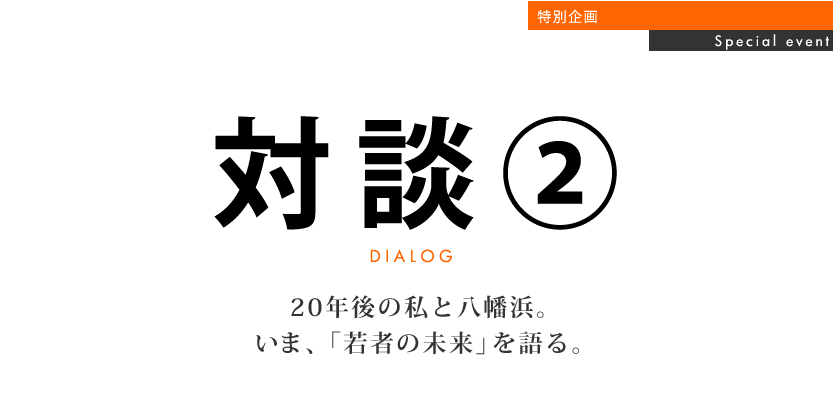・高校生版いろは塾『未来創造セミナー~20年後の私と八幡浜~』イベント取材記事
・アンケート結果について
いろは塾で高校生に進路についてアンケートを取ったところ、進学したいという方がほとんどでした。
地元で働きたいという方は、親が左官や消防士だったりする方でした。
ただ、今回のいろは塾を行ってみて、都会に就職しても、いつかは八幡浜に帰ってくるのもいいかなと思っていただいたようです。
実際、八幡浜青年会議所にもそういった経歴のメンバーが多いので、彼らの話を直に聞いて、将来は地元に帰ってもいいかなと思っていただけたようです。
高校生に故郷の良さを知ることは大切だということを伝えられたことや、改めて自分たちのことを深く考える機会を与えられる本当にいい機会だったと思います。
また、高校生は進学するにしろ、就職するにしろ、いずれにしても明確なビジョンを持っていると感じました。
それは就職のことだけではなく、結婚(25歳から28歳までにしたい)であったり、子どもの数(二人がいいなど)であったり、年収(500万円程度を希望など)であったりと、将来のことについてそれぞれが具体的なビジョンを持っていました。
私たちのような青年と高校生が会う機会は意外とないので、私たちも刺激的でしたし、高校生たちにとってもすごく刺激的だっただろうと思います。
高校の先生方からもすごく楽しかったというお声もいただき、高校の土曜教育が48日間あるので、地域のディレクターとして話をしに来てくれないかというお話もいただきました。
実際、この事業を企画したメンバーが、川之石高校でお話をする機会もいただきましたので、八幡浜にもこんな仕事があるのだよということをもっと伝えていかなければいけないと思っています。

高校生を対象に事業をしてみて手ごたえはありましたか?
銀行員や公務員、水産業や農業に携わっている人、社長など、さまざまな立場の方から話をさせていただいたのですが、高校生が将来について考える上で、先生が教えるのではなく、先輩が自分の体験を伝えることで、自分ならどうしただろうと置き換えて考えることができたという感想がありました。また、今回の「いろは塾」では、最初に八幡浜青年会議所のメンバーのやっている仕事の紹介をしたのですが、高校生はこの部分にすごく興味をもっていました。
最初は、「八幡浜には農業か漁業か公務員しか仕事がないんでしょ」と言っていましたが、「八幡浜にもこんなに仕事があるのですね」と驚いていました。
そして、「八幡浜でも働けるのですね」と理解していただいたことが大きな手ごたえでした。今回は、高校1年生を対象とした事業だったのですが、事前取材で3年生にヒアリングに行ったところ、高校生に地元に戻ってきてもらいたいと思っても、大きい就職先がかなり厳しいと感じました。
大手になるとボーナスが6カ月分とかになるので、中小企業では勝てない。
今ある企業がより高収益を出せる企業になっていかないと人は戻ってこないなと感じました。
生活をしていく上では、年収500万ないといけないというわけではないのだけどね。
そうですね。
ただ、同条件で採用が決まった場合などは負けてしまいます。
私の会社でも、4月と5月には結構内定を取っていたのですが、8月に大手の採用が解禁になり、大手が内定を出すと、内定を辞退をさせてほしいと連絡が相次ぎました。
出身が南予の方も18人採用予定だったのですが、その半分が辞退しました。
学生の意見を聞いていると、八幡浜にも企業があるのですね、知りませんでした、というのが率直な意見なようです。積極的に松山や県外で、こういう企業があるんですよということをPRしていかないと、なかなか知る機会がないのが現状です。
今回は、その前段階、高校生のときに八幡浜にも仕事があるのですよということを知ってもらっておくということで意味のあることだと感じています。
市長として、若者がこっちに帰ってくるような起爆剤はありますか?
若者が八幡浜に帰ってくる施策として、企業を外から引っ張ってくるというのは、土地がなく、上下水道の値段もある程度することから八幡浜では難しいと考えています。
だから、今の話からすると、八幡浜の企業を君たちと一緒になってPRしていく、八幡浜にもこんな産業がありますよ、みかんと魚だけではないですよ、というところも提供していかないといけないなと思います。
しかし、本当に一番何が必要かと言ったら、今まで根付いている農業や漁業をしっかりしていくことが回り道に見えても一番の近道だと考えています。
ここには、本当に力を入れていかないといけないと考えており、今後も、色々な対策をして、Iターン、Uターンしても働ける場所を確保していきたい。
農業や漁業では加工場などを造ることで、裾野の広い産業に育てていかなければと考えています。
もちろん農協や漁協と一緒になってアイデアを出しながら、例えば若い人でも就農したことがない人でも、みかん作りができるような基盤づくりをしていくという事が大切だと思います。
1次産業から仕事をつくるということで、地方創生でも触れられていましたが、直売所などはどうでしょうか?
直売所はほしいですね。
八幡浜はみかんと魚のまちで、魚は、どうーや市場とどーや食堂を整備して、多くの人に足を運んでいただいています。
松山市、今治市や四国中央市からもお客さんに来ていただいているという話を聞いています。しかし、みかんは、これだけ有名なのに、市内でみかんを買うところがない。
やはり直売所みたいなところがあれば、1~2億ぐらいの売り上げが期待でき、さらにそこで働く機会が生れる。
今後も、みかんと魚にはとことんこだわりたいので、アイデアをいっぱい出して、さまざまな方策を掘り起こしていきたい。

市長は、まちをデザインするということをよく考えられていますよね。
新しいデザインでいうと、今回、新たに温泉も出ました。
温泉は一つの目玉になりますね。
今後のまちづくりに温泉も活用していかないといけないですね。
温泉に限らず、最近、八幡浜は、民間企業でも変わってきていますよね。北浜にフジができ、江戸岡のフジもリニューアルし、市内中心部の電器屋跡も改修が始まるなど。
福利厚生も年間休日も108日程度は当たり前にやらないといけない時代です。
個人的には、託児所がほしいです。民間が運営する託児所があったらいいなと思います。
来年度から白浜保育所が民営化になり、土・日も子どもを預けることが可能になります。
夜間もある程度は対応できるようになるし、あとはどこかに病児保育や病後児保育ができるようになればと思います。
小学生や中学生の育成についてはどうお考えですか。
いつか八幡浜に帰ってきたいと思えるような愛着心や地域愛を育んでいけるような教育を行いたいと考えており、子どもの頃に感動を覚えるような体験や一流・本物に触れてもらう機会を提供することが大切だと考えています。
そのため、市では、一流のオペラ、ジャズ、ピアノのコンサートなどで各学校を回ってもらっています。
特に市制施行10周年である今年は、富士美術館から普通では一生見られないような絵画61点をもってきていただき、子どもたちを含め多くの方に楽しんでいただきました。
今後も子どもたちに本物をしっかり観てもらい、感じていただける機会を増やしていきたい。
現在、坊ちゃん劇場には、本市出身の二宮忠八を題材にした演劇で、各学校を回ってもらっているほか、来年は坊ちゃん劇場と市民劇団で二宮忠八のミュージカルを行うことにしている。
八幡浜がどういうところで、どういう人がいて、こんな環境だからおいしいみかんができて、魚も獲れて、二宮忠八さんや二宮敬作さんが出てきたのだよ、というような地元に対する教育は地域愛を育むことにつながるし、将来も八幡浜のことを気にしてくれるようになると思います。
現在は、小・中学生は土・日が休みだけれど、今後これをどうするかも課題だと思っています。新しい教育員会制度が始まり、市長のもとで総合教育会議を開催するようになるので、授業に変わる何かを教える機会を設けることも考えたい。
その時間を使えるなら、青年会議所でも事業をしてみたいですね。
八幡浜青年会議所のメンバーも青少年を対象とした事業を実施していますが、やはり事業の理念を真剣に考えるようになっていて、企業もまちもそうだけど、一生懸命どうしないといけないかということを考えないといけないですね。
どこの方向に向かっていくかはすごく大切なことですね。
秋のお祭りなど、子どもたちにしっかり参加してもらって、八幡浜の歴史や伝統を楽しみながら成長してもらいたいと思います。
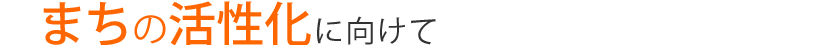
まちの活性化に向けて、どのような取り組みがありますか。
仕事をつくるということについては、Iターン、Uターンも含めて、農協・漁協・企業などと一緒になって対応していく考えです。
水産については、新たにシーフードセンターを造り、水産物の加工はしているのですが、今はまだ販路としての出口が見つかっていないのが課題です。
最近は、ふるさと納税で市の産品がよく出ているので、市の特産を知ってもらうという機会として捉えたい。
また、今回、台湾にも視察に行ってきたのですが、今後は、海外のマーケットも視野に入れていきたい。
八幡浜には、日本一のものがたくさんあるので、台湾に軸足をおいた戦略も検討したい。
実際、八幡浜青年会議所の先輩には、みかんを松山から船で台湾に送っている方がいますが、港の整備が終われば、そのうちの何回かでも八幡浜から送れるようになればいいなと思っています。
台湾を視野にいれるのは面白いですね。
親日ですし、サイクリングのつながりもあるので、販路の出口として期待できますね。
産業の面で言えば、南予一円で事業継承システムという取り組みも行っています。
事業所に跡継ぎがいなくなってきているので、こういった事業があるというのを調べて、都会の人に継いでもらえるようにする取り組みです。
結婚・出産の支援に関する取り組みはどうですか。
まだ一組も成立はしていませんが、縁結びコーディネーターを設置しており、これにより、お付き合いされている方はいると聞いているので、今後に期待しているところです。
結婚に向けては、周りのサポートも必要だと感じているので、縁結びコーディネーターの下にサポーターなどを作って情報を寄せ合っていくことも検討したいと思っています。
出産については、結婚しても子どもができないという人も多いので、来年からは、不妊治療の補助制度をつくって支援していきたいと考えています。
最後に、人口減少への対策として、新しい人の流れをつくる取り組みはありますか。
人の流れは、「みなっと」ができてから、だいぶ変わったと思っています。
また、温浴施設もできたら滞留時間が長くなると期待しています。
来年から取り組むことで言えば、松村正恒さんが名誉市民になり、松村さんの建築物や木造校舎が結構残っているので、これらの木造建築群を結んで、外から見に来てもらうような観光・地域づくりに関する取り組みをする予定です。
愛媛大学の教授などにも参画してもらい、歴史のあるのものをどう活用するか、市民会館の跡地をどう活用するか、ということを考え、デザイン的にもどう残していくかということを考えて、新しい人の流れをつくりたいと考えています。
新しい取り組みで言えば、先般のサイクリング佐田岬もたいへん好評だったと聞いています。
参加者からは本当によい評価をいただきました。
エイドステーションも充実しており、伊方町の町見地区では「冷やし金太郎芋」が、三崎港の昼食では「シラス丼」、きらら館では「甘酒アイス」、八幡浜に帰ってきたら「ちゃんぽん」と「鯛めし」、道中では地元の人が「いりこ」を配っていたりと、その土地ごとに、たいへんなおもてなしをしていただき、感謝しています。
新しい人の流れがきていますね。
新しい人の流れでも、まずは、地域の中で流れを作って連携していく形を大切にしたいと思っています。
八幡浜には17の地区公民館がありますが、この公民館単位でそれぞれにブラッシュアップしていくと、各地域には地域の方々の想いがこもった良いものがいっぱいありますので、これを繋いでいけたらと思っています。
今年は、宮内地区公民館を設計して来年には建築し、その後には、川之石地区公民館を造っていきますが、やはり地域に拠点ができたら、地域の人たちが活発になってくるし、お互いに切磋琢磨できると思います。
互いに意識し合ってどんどん成長してもらうと、それだけでまちに活気がでてきます。
新しい宮内地区公民館の隣りには、農産物の加工場を造ろうと思っているのですが、これはジュースなどではなく、主婦層がジャムやスイーツ等、色々なことができるよう、その可能性に期待しています。
川之石地区では、地元の景観を利用して川と美名瀬橋をイメージした親水公園的な公民館を造りたいとの意見がありますので、地域交流拠点施設といった形でやれば、「みなっと」と繋げて、おもしろいことができるのではないかなと思います。
まずは、八幡浜の中での行き来、八幡浜の人が行きたいと思うところこそ、外から人を呼んでこられると思うので、地域の方々と協力して誰もが集える楽しい場所をつくっていきたいと思います。
私達も八幡浜に住んでいる皆さんに、八幡浜も楽しいと思っていただけるような気付きを与えることができるような事業をしていかないといけないと思いました。
市長も若いので、僕たちも頑張らないといけないですね!
一緒になって、明るく元気で楽しいまちづくりに取り組みましょう!